大切な家族である愛犬にはいつまでも健康でいてほしいものですよね。ところで、みなさんは犬が歯磨きをしないとどうなるのか、知っていますか?実は、歯磨きと犬の健康には、大きな関係があるのです。
本記事では、犬が歯磨きをしないとどうなるのかということのほかに、歯磨きの方法や頻度、おすすめのアイテムなどを詳しく紹介しています。
愛犬の歯磨きに悩んでいる方やこれから犬と一緒に暮らしたいと考えている方に、必見の内容となっていますので、ぜひ最後まで読んでいってください。
- 愛犬の歯磨きをしないとどうなる?
- 愛犬の歯磨きはいつからはじめるべき?
- 愛犬の歯磨きのやり方を解説!
- 愛犬の歯磨きはどれくらいの頻度で行うべき?
- 愛犬の歯磨きを成功させるポイントとは?
- 愛犬の歯磨きをするのに便利なアイテム4選
- 愛犬の困りごとなら「バデッジ」がおすすめ!
愛犬の歯磨きをしないとどうなる?
犬の健康と歯磨きをしないことが大きな関係があるなんて、半信半疑の方もいるでしょう。本章では、「愛犬の歯磨きをしないとどうなるのか?」について細かく解説しています。
愛犬が歯磨きをしていないと、歯だけではなく、内臓や骨にも影響が出てくるのです。「もっとしっかりと歯磨きをしておけば良かった…」なんてことにならないためにも、犬の歯と健康についてしっかりと知っておくことが大切です。具体的に愛犬の歯磨きをしないとどうなるのかというと、以下の3つのことが考えられます。
・歯周病が発生する
・歯周病により骨に影響が出る
・歯周病により内臓に影響が出る
それでは、これらのリスクがどのように起こるのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。
歯周病が発生する
まず、犬が歯磨きをしないとなると、歯周病が発生します。人間も歯磨きが不十分だと歯垢が溜まり、それが原因で歯周病が発生します。
人間の口の中は約pH6.8の中性に近い弱酸性と言われていますが、犬はpH8〜9の弱アルカリ性です。歯周病菌はアルカリ性の環境のほうが活動しやすいため、犬の方が人間よりも歯周病になりやすいのです。
歯周病のもとになる歯垢や歯石は、実は細菌のかたまりです。たまった汚れの歯垢がだんだん固くなって「歯石」になります。歯みがきをしないでいると、この歯石がどんどん増えて、歯と歯ぐきのすき間に入り込み、炎症を起こしてしまいます。
これが進むと「歯周病」という病気になるのです。歯周病の兆候として、口から腐ったようなニオイがしたり、くしゃみや鼻水が出たりします。
ほかにも、口を気にしていたり、噛む時に痛がっていたりした場合は、要注意です。
歯周病により骨に影響が出る
歯周病が進行すると、歯を支えているあごの骨や歯ぐきがどんどん弱くなり、「歯槽膿漏」という状態になります。歯槽膿漏になると、歯ぐきが腫れたり出血したりするだけでなく、歯そのものがグラグラしてくるようになり、最終的には自然に抜け落ちてしまうこともあります。
下あごの歯周病がひどくなると、歯を支えている骨の一部がもろくスカスカな状態になってしまいます。
すると、硬いものをかんだときや、ちょっとした衝撃でも骨が耐えきれず、あごの骨が折れてしまうという深刻な事態につながるのです。これはとくに高齢の犬や小型犬に多く見られ、食事が取れなくなるなど生活に大きな支障をきたすこともあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、日頃からの歯磨きが非常に重要です。
歯周病により内臓に影響が出る
歯周病が進行すると、影響が出るのはあごの骨や歯ぐきだけではありません。とくに注意が必要なのが、歯ぐきの炎症によってできた傷口から細菌が血管内に侵入してしまうことです。
血液は全身をめぐっているため、一度入り込んだ細菌は、口の中だけでとどまらず、全身に運ばれてしまいます。その結果、細菌が心臓や腎臓、肝臓などの重要な臓器にたどり着き、心内膜炎や腎炎などの深刻な病気を引き起こす可能性があります。とくに、もともと内臓に疾患を持っている犬や高齢犬では、全身への影響が大きくなるリスクが高いため、より注意が必要です。
上記に記述したように、歯周病は歯だけでなく、犬の健康に大きな影響を与えます。歯周病は「口の病気」と思われがちですが、体全体の健康にも深く関わっていることを念頭において、歯磨きで早めの予防とケアを心がけることが大切です。
愛犬の歯磨きはいつからはじめるべき?

愛犬が歯磨きをしないとどうなるのか、イメージできたら、歯磨きをはじめる時期について考えてみましょう。愛犬の歯磨きは、家族に迎え入れて環境に慣れたと判断できたらはじめましょう。
まだ乳歯の時期であっても、早すぎるということはありません。小さいうちから少しずつ慣らしていくことで、永久歯に生え変わる頃にはお口のケアを嫌がらないようになってくれる可能性が高くなります。
また、歯磨きに対する「怖い」「嫌だ」といったネガティブな印象を持たせないことが何より大切です。たとえば、口元を触ったあとに褒めたり、軽く歯に触れた後にご褒美をあげたりするなど、楽しい体験と結びつける工夫をするとスムーズです。
成犬になってからお迎えした場合でも、急がずに、その子のペースに合わせて丁寧に練習していきましょう。焦って無理に進めてしまうと、かえってケアを嫌がってしまうこともあります。
毎日少しずつステップを踏んで慣れていくことで、愛犬にとっても飼い主さんにとっても、負担の少ない歯磨き習慣を身につけることができます。歯磨きは、愛犬のペースに合わせて無理なくはじめることがおすすめです。
愛犬の歯磨きのやり方を解説!

ここまで、犬が歯磨きをしないとどうなるのか、歯磨きをはじめる時期について紹介してきました。愛犬が歯磨きをしないとどうなるのかという危険性を理解しても、具体的にどのように歯磨きを行えば良いかわからない方もいるでしょう。
歯磨きのステップは、以下の5つにわかれます。
①口元を触られることに慣れさせる
②歯や歯ぐきにも触れたらご褒美をあげる
③指を口の中へ入れられたらご褒美をあげる
④指磨きをする
⑤歯ブラシで前歯から順番に磨いていく
本章では歯磨きのやり方を一つひとつ解説しますので、ぜひ参考にしてください。
①口元を触られることに慣れさせる
愛犬と過ごしていて、口元を触る機会は多くありません。しかし、歯磨きに慣れてもらうためには、口元に触れられることに抵抗を感じさせないことが大切です。
そのため、普段のスキンシップの中でさりげなく口元に触れ、触らせてくれたらすぐに優しく褒めてあげましょう。
おやつなどのご褒美を使うのも効果的です。最初は唇の端など小さな範囲から始め、少しずつ歯ぐきや歯の近くまで触れる範囲を広げていくことで、ストレスをかけずに慣らしていくことができます。
②歯や歯ぐきにも触れたらご褒美をあげる
まずは1本の歯に触れさせてくれたら、すぐにご褒美をあげて「歯に触られる=良いことがある」と覚えてもらいましょう。この時、前歯よりも比較的触られても嫌がりにくい犬歯からはじめるのがおすすめです。
いきなり長時間触るのではなく、短時間・少しずつの練習を繰り返しましょう。慣れてきたら徐々に触れる歯の数を増やしたり、歯ぐきにも軽く触れてみたりしてください。無理に進めると嫌な印象が残ってしまうので、愛犬の様子を見ながら、リラックスしているタイミングで行うことがポイントです。
③指を口の中へ入れられたらご褒美をあげる
次のステップは、指を口の中に入れることです。最初は無理せず、おやつを持った手で注意を引きながら「待て」と声をかけ、軽く唇をめくる練習から始めましょう。
この時、犬が落ち着いていられるように優しく声をかけるのも効果的です。唇をめくることができたら、すぐにたくさん褒めて、おやつを与えてあげましょう。愛犬が「口元を触られることは嫌じゃない」と感じられるようにすることが目的です。
慣れてきたら、少しずつ歯や歯ぐきに指が触れる時間を延ばしていきましょう。
④指磨きをする
いよいよ歯磨きの段階です。とはいえ、いきなり歯ブラシを使うのではなく、まずは指にペーストをつけて、指磨きから始めましょう。この時、無理にこすろうとせず、ペーストを歯にちょんとつけるだけでも十分です。
この段階のポイントは、歯にペーストが触れる感覚に慣れさせることです。指でのケアに慣れてくると、次のステップである歯ブラシへの移行もスムーズになります。焦らず、愛犬の様子を見ながら少しずつ進めていくことが成功のカギです。
⑤歯ブラシで前歯から順番に磨いていく
指磨きに慣れたら、歯ブラシで磨きます。最初は歯ブラシを持った手でおやつを与えることで、「歯ブラシ=良いことがある」と感じてもらうと良いでしょう。この流れを繰り返しながら、少しずつおやつがなくても歯ブラシに対して嫌がらない状態を目指しましょう。
歯ブラシに慣れてきたら、ペーストをつけた歯ブラシで前歯から少しずつ磨いていきます。どうしても歯ブラシを嫌がってしまう場合は、犬用の歯磨きジェルの中から好きなフレーバーのものを使用して、良い印象をつけてあげるのも一つの方法です。
慣れてきたら徐々に奥の歯も磨いていき、おやつをあげて、褒めてあげてください。
愛犬の歯磨きはどれくらいの頻度で行うべき?
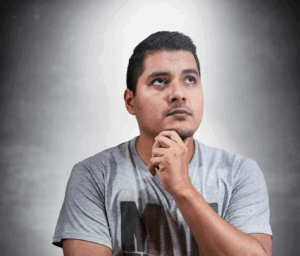
前述したように、犬の方が人間よりも歯周病になりやすい傾向にあります。人間では歯垢が歯石になるまでに約12日かかるとされていますが、犬の場合はわずか3〜5日で歯石へと変化すると言われています。
このスピードの違いから考えても、愛犬の歯磨きは毎日行うことが理想的だとされています。しかし毎日の歯磨きは、飼い主さんにとっても、愛犬にとっても大変なことです。そんな時は、最低でも週に2〜3回を目安に行いましょう。
「歯磨きは毎日行うのが理想だから、毎日してあげないといけない」と、飼い主さんが気負い過ぎるのも避けたいものです。飼い主さんの緊張感から、愛犬にもプレッシャーが伝わってしまい、歯ブラシを嫌がってしまう可能性もあります。そのため、完璧を目指しすぎず、できる範囲から無理なく取り組むことが大切です。
歯磨きをしつけや義務として捉えるのではなく、日々のスキンシップの延長として、愛犬との楽しい時間の一部にすることを意識しましょう。おやつを使ってリラックスした雰囲気をつくったり、歯磨きの後にたくさん褒めてあげたりすると、なお良いでしょう。
愛犬の歯磨きを成功させるポイントとは?

犬によって、歯周病になりやすい体質だったり、口元を触られるのが苦手だったりと、歯磨きに対する反応はそれぞれ異なります。可能であれば毎日歯磨きをしたいものの、うまくいかないこともあるでしょう。とくに、歯磨きに慣れていなかったり、過去に嫌な思いをした経験があったりすると、歯磨きが大きなストレスになってしまうこともあります。
しかし、少しの工夫とコツを取り入れることで、愛犬との歯磨きタイムがよりスムーズで楽しいものになります。実は、愛犬の歯磨きを成功させるポイントがいくつかあるのです。こうしたポイントを意識するだけでも、毎日の歯磨きは大変というイメージから、少しずつなら続けられそうという気持ちに変わっていくでしょう。
本章では、以下の3つのポイントに焦点をあてて、無理なく、楽しく歯磨きを行うための方法を詳しく紹介します。
・愛犬にストレスを感じさせない
・「歯磨きは楽しい」という印象を持たせる
・愛犬が嫌がるときに無理やり歯磨きしない
愛犬の歯磨きに悩んでいる飼い主さんはぜひ参考にしてください。
愛犬にストレスを感じさせない
母犬が子犬を叱るときに口をくわえるように、犬にとって口元はとても敏感でデリケートな場所です。
そのため、急に触られると驚いたり、不快に感じたりして、強い警戒心やストレスを抱いてしまうことがあります。
いきなり口元を触って歯ブラシをすると、愛犬がストレスを感じてしまいます。そのため、歯磨きの習慣づけは、愛犬の様子をよく観察しながら、焦らずに段階を踏んで進めることが大切です。まずは口の周りに触れることからはじめ、触られても平気になったら、指で歯に触れてみる、といったように少しずつ慣らしていくことが成功のカギとなります。
このようなステップを踏むことで、愛犬が歯磨きを怖がらず、飼い主さんとの信頼関係の中で安心してケアを受け入れてくれるようになるでしょう。
「歯磨きは楽しい」という印象を持たせる
できれば口元を触ってほしくない愛犬に対しては、「歯磨き=怖い・嫌なこと」ではなく、「楽しい・うれしいこと」と思ってもらえる工夫がとても大切です。そのためには、歯磨きのステップごとに成功体験を重ねることがポイントになります。
たとえば、口元に軽く触れられたらおやつをあげたり、唇をめくれたら褒めたりしてあげましょう。指で歯に触れられたらさらにご褒美、というように、小さなステップごとにたくさん褒めて報酬を与えることで、少しずつ良いイメージを持ってもらいましょう。
また、歯磨きのトレーニングは短時間で終わらせることを心掛けると、なお良いでしょう。長時間トレーニングを続けていると愛犬が疲れてしまい、歯磨きに対して苦手意識を持ってしまう原因にもなりかねません。楽しくて無理なく、ご褒美たっぷりというポイントを抑えて進めることで、愛犬も徐々に歯磨きに慣れ、「歯磨きって楽しい」と思えるようになっていきます。
愛犬が嫌がるときに無理やり歯磨きしない
几帳面な飼い主さんほど、歯磨きを完璧にしようとしがちですが、無理に進めてしまうと、かえって愛犬が歯磨きを嫌いになってしまう可能性があります。たとえ全部の歯を磨けなかったとしても、愛犬が嫌がる素振りを見せた時は、思い切って途中で中断してしまいましょう。
大切なのは、愛犬が「歯磨き=怖くない・嫌いじゃない」というイメージを持ってくれることです。
場合によっては、飼い主さんが歯磨きを中断したりお休みしたりする勇気も大切です。
無理せず、愛犬のペースで継続させることを意識しましょう。
また、「今日はここまでできたね!」とポジティブな気持ちで終えることも重要です。
毎回少しずつの成功体験を重ねていくことで、自然と歯磨きへの抵抗も減っていくことでしょう。
愛犬の歯磨きをするのに便利なアイテム4選

愛犬の歯磨きを行うにあたり、毎回細かく丁寧に磨いてあげるのは理想的です。しかし忙しい日が続いたり、体力的に厳しい日が続いたりすると、飼い主さんにとって負担になってしまうこともあるでしょう。無理に続けようとすると、お互いにストレスを感じてしまい、歯磨きの時間が苦痛なものになってしまう可能性もあります。
そんな時は、デンタルガムや液体デンタルケアなどの便利なアイテムを上手に活用することがおすすめです。毎日の本格的な歯磨きが難しい日でも、このようなアイテムを使えば、口の中を清潔に保つことができます。
また、アイテムによってはご褒美感覚で使えるものもあるので、愛犬自身も楽しみながらケアを受け入れやすくなるというメリットもあります。
本章で紹介する便利なアイテムを取り入れつつ、無理せずに続けられることを第一に考えて、愛犬と一緒に歯磨きを楽しんでいきましょう。
①デンタルガム
デンタルガムは、おやつタイプのアイテムです。商品によっては、天然の牛皮をミルク風味に味付けしていたり、55%以上がお肉でできていたりと、愛犬が喜んで噛める工夫がされています。食べているうちに歯垢や歯石の沈着を抑えてくれたり、噛むごとに歯茎や歯を丈夫にしてくれたりと、歯周病の予防もしてくれます。
ポイントは前の歯ではなく、上顎の奥の歯を使ってしっかりと噛ませることです。
口の横から手を入れてあげると、効果的です。
おやつタイプのアイテムは、愛犬に与えっぱなしだと効果が下がってしまうので、飼い主さんが手に持ったまましっかり時間をかけて噛める工夫をしてあげましょう。
②液体デンタルケア
飲み水に混ぜられる液体デンタルケアも、歯磨きに便利なおすすめアイテムです。商品によっては、適量を測れる計量カップが付属しており、100倍などに希釈して飲ませてあげます。普段通りに愛犬に飲んでもらうだけなので、時間がない朝でも手軽に用意できます。
成分や効果も商品によって様々なので、愛犬に合ったものを選んであげましょう。
③フレーバー付き歯磨きペースト
フレーバー付き歯磨きペーストをおすすめする理由は、商品によって様々な味が選べ、愛犬にとっても歯磨きが楽しくなるようなアイテムだからです。犬が好みやすいチキン味をはじめ、バニラ味やシーフード味などもあります。さらに食物アレルギーに対応した商品もあるため、愛犬にぴったりなフレーバーが選びやすいでしょう。
基本的に酵素が含まれていて、歯垢を落とす能力が高いため、歯石や歯周病の発生リスクを抑えることが可能です。
さらに、すすがないで使用できるものが多いので、飼い主さんにとっても扱いやすいアイテムです。
④デンタルブラシ
愛犬に歯磨きをしないとどうなるのか紹介したように、歯磨きをしないでいると歯周病になり、その影響で骨や内臓にまで支障が出てきてしまいます。そのため歯磨きで最も大切なのは、歯周病の原因となる歯垢や歯石を取り除くことです。歯磨きの際は、歯の表面だけでなく、歯周ポケットまで磨いてあげることがポイントです。
愛犬の歯を隅々まで磨くのに適しているのが、デンタルブラシです。愛犬の状態に合ったタイプのブラシを選んであげましょう。飼い主さんが歯磨きしやすいように、持ち手が握りやすく工夫されているものもあります。
殺菌加工されているデンタルブラシだと、衛生面でも安心して使用できます。
愛犬の困りごとなら「バデッジ」がおすすめ!

本記事では、愛犬が歯磨きをしないとどうなるのかということや具体的な歯磨きの方法、便利なおすすめアイテムなどを詳しく紹介してきました。「これまで、愛犬が歯磨きをしないとどうなるのか具体的に想像できていなかった…」という方も、歯磨きの大切さを再認識できたのではないでしょうか?
歯磨き以外にも、たとえば虫トラブルや耳掃除など、大切な愛犬と暮らす中で悩みごとがある飼い主さんは多いのではないでしょうか?
そんな飼い主さんの悩みごとや困りごとを解決するのにおすすめなのが、「ペット通信バデッジ」というサイトです。愛犬に加えて、愛猫も快適に生活できるために役に立つ記事が200個以上紹介されています。
愛犬・愛猫の困りごとを解決したい方やペットシッターの利用を検討している方は、ぜひ一度「バデッジ」をのぞいてみてください。
バデッジについて詳しく知りたい方はこちら

